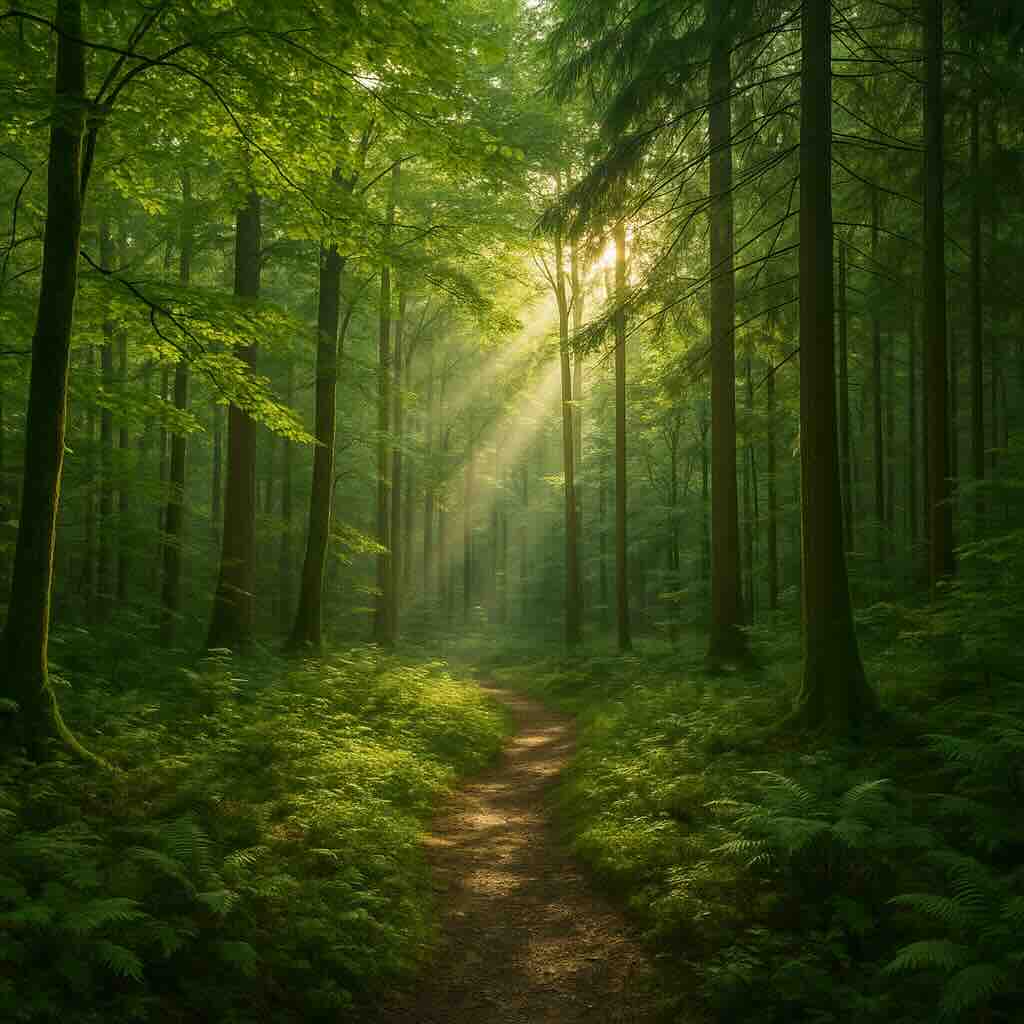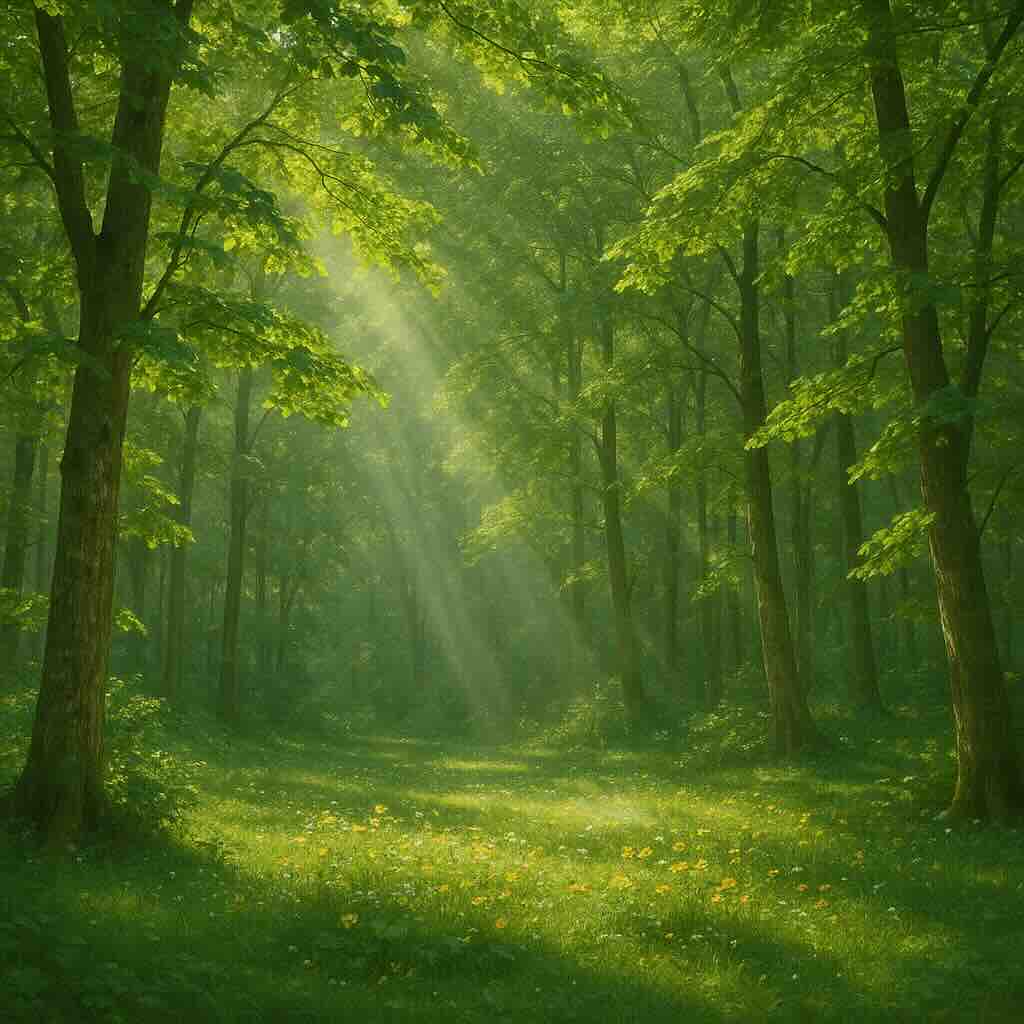樹木を知ろう
”なぜ木は枯れるのか”についてのコラム
樹木を20年間見つめてきた代表の樹木への考え方、自然との関わり方を個人の視点で綴ります。
コラム・随想第2回目は、近年の気候変動による樹木が枯れる現象について掘り下げて考えてみます。

水と樹木
30mを超える樹木の樹冠に、どうやって根から水を運んでいるかご存知だろうか。
かつては、毛細管現象や、根からの押し上げで水を運んでいたと考えられていましたが、現在では、葉からの水分の蒸散による負圧と、導管内に満たされた水が切れることなく連続して引き上げられる“連続水柱”によって、水が上部まで運ばれているという説が、もっとも有力で広く支持されています。樹木は、土壌から根を通じて吸収した水を、導管(広葉樹)または仮道管(針葉樹)を通り、幹・枝・葉まで運びます。導水系は主に木部内に位置し、死細胞の管が連なって水を輸送します。(死細胞が連なる木部とはつまり、乾燥した状態では私たちが“木材”と呼んでいる部分そのものです)。
葉の気孔からの蒸発(蒸散)により、水分が失われると導管内の水が引っ張られるように移動します。これにより、根から葉への一方向の水流が生じます。 導管内の水は、分子間の凝集力によって切れ目なく連なっており、さらに導管壁との付着力によって支えられています。この連続した水柱が、30m以上の高さまで水を持ち上げることを可能にします。 蒸散のイメージは霧吹きに例えられ、掃除機のように空気(大気圧)で水を吸い上げるのではなく、水で水を引き上げる状態となり、前者では10mほどが引き上げの限界に対し、後者では100m以上も水を引き上げることができます。

土と樹木
樹木が健全に生育するためには、適切な土壌環境が欠かせません。土壌は鉱物質・有機物・空気と水の三要素から構成されており、それぞれが根の成長や機能に影響を与えています。
土壌は物理的には、固相(鉱物質・有機物)、液相(水)、気相(空気)の三つの相に分けられます。固相は土壌の骨格を構成し、液相は根に水と可溶性養分(リン酸、カリウム、硝酸態窒素など)を供給し、気相は根の呼吸に必要な酸素を供給します。これら三相のバランスが取れていることが、健全な土壌環境の木の基本となります。
鉱物質は土壌の粒径(砂・シルト・粘土)によって通気性や保水性を左右し、有機物は水分保持や養分供給の働きを担います。また、土壌中の空隙には水と空気が共存しており、根はこの空間から酸素と水分を同時に吸収しています。
樹木の生育環境に適した土壌の性質は、根の呼吸や水分ストレスへの耐性に直結し、過度に締まった土壌では酸素が不足し、また排水不良は根腐れの原因となります。逆に保水性が低すぎると乾燥に弱くなり、土壌が硬すぎる場合は、根の伸長が妨げられることもあります。
根は通気性や有機物の多い表層に集中しやすく、水分や養分を求めて横方向にも広がります。立木の枝張りよりも広い範囲に根が及んでいることが多く、地下の空間全体が重要な成長基盤となっています。
土壌の化学性では、樹木は一般的に弱酸性から中性のpHを好み、極端な酸性やアルカリ性では必要な養分が吸収しづらくなります。また、窒素・リン酸・カリウムなどの主要な養分のバランスや塩類濃度も重要であり、過不足は成長や樹勢に大きく影響します。
植えられている立地条件でも土壌環境は左右し、斜面の上下での水分状況の違いや、土壌の深さ、造成などの人為的な影響によって、同じ樹種でも生育状況が大きく異なることがあります。
このように、土壌は樹木の根を支えるだけでなく、その健康と成長を左右する極めて重要な要素であるといえます。

菌と樹木
樹木が育つ土壌には、実に多様な微生物が存在しており、その中でも「菌」と総称される真菌類(カビやキノコ)、酵母菌などは、樹木と切っても切り離せない関係にあります。これらの菌は、放線菌や細菌類を含めた微生物群とともに、土壌環境を形成しております。
菌の役割は多岐にわたります。まず第一に、枯葉や動植物の遺体などの有機物を分解し、植物が吸収できる形の養分(窒素・リン・カリウムなど)へと変える働きがあります。そして、菌糸が土粒子を絡めることで団粒構造を形成し、土壌の通気性や保水性を維持しております。
「菌根」と呼ばれる菌との共生関係では、特定の菌根菌は樹木の根と結びつき、水やリン酸を供給する代わりに、樹木から糖分を受け取るという互恵関係を築いています。この関係は、栄養の乏しい環境においても樹木が健全に成長する上で極めて重要です。
しかし、すべての菌が樹木にとって味方というわけではありません。一部の菌は、ストレスを受けた樹木に寄生して病気を引き起こします。根腐れや立枯病の原因となるフザリウム菌やリゾクトニア菌などがその代表です。また、落ち葉や枯れ木といった死んだ有機物を主な栄養源とする腐生菌も、時に生木にまで影響を及ぼすことがあります。
このように、菌と樹木の関係は「共生」「寄生」「腐生」と多様であり、土壌においても私たちがよく知る、善玉菌と悪玉菌がいることがわかります。菌は、時として脅威となり、また時には樹木と共に生き、支え合う存在でもあるのです。
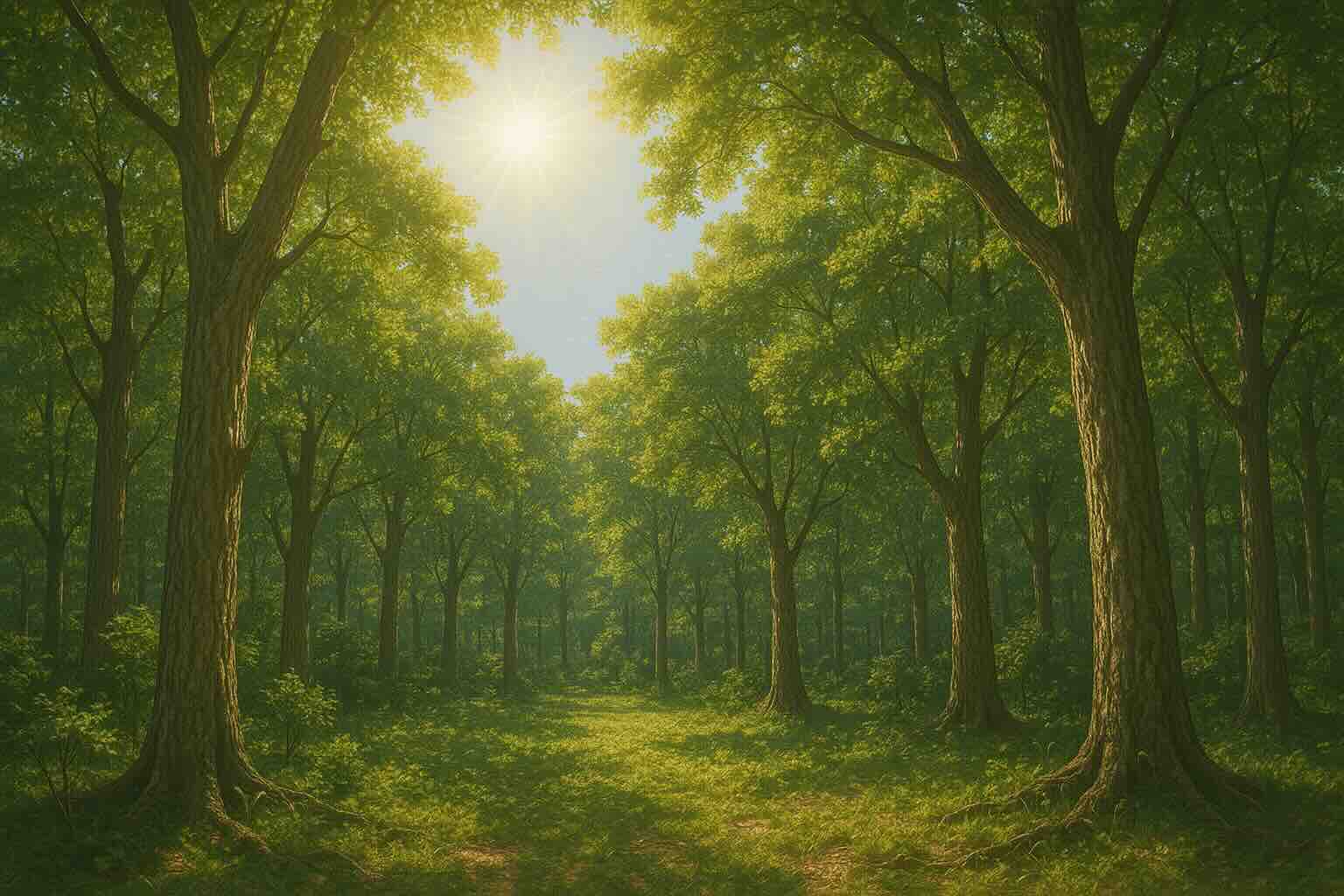
気温と樹木
樹木の生存と成長には、温度が大きな影響を与えます。気温が高くなると、樹木の蒸散活動が活発になり、葉からの水分の放出が急激に進み、同時に根からの水の吸い上げがどんどん促進されます。一方で、猛暑などにより強烈な蒸散が続く際に、土壌内の水分の枯渇が起こると、導管内に気泡が発生するキャビテーション(連続水柱の破綻)が起こることがあります。このキャビテーションは水の連続性を断ち、結果として導水障害を引き起こします。これが継続し深刻化すれば、枝枯れや樹木全体の枯死や衰退につながります。キャビテーションは一度起こると回復は困難となることから、キャビテーションを起こさない環境づくりが必要となります。
反対に、気温が低くなると、凍結によるリスクが現れます。樹木内の水分が凍ることで体積が増し、細胞や導管が物理的に破壊される「凍裂」が発生することがあります。特に冬季の晴天で日中に幹表面が温まったり、気温が高い日が続き水の吸い上げが起こった後に、夜間などに急激に冷えると、膨張と収縮の差が大きくなり、幹に亀裂が入ります。この凍裂は外部から見える裂け目として現れ、病害虫や空気中の菌の侵入口にもなり得ます。
また、高山における森林限界では、低温と強風という過酷な気象条件が樹木の成長に影響を与えます。標高が高くなるにつれ気温が低下し、樹木の光合成や呼吸が難しくなり成長が阻害されます。さらに、強風による枝葉の損傷や風乾による乾燥、積雪の吹き飛ばしによる地温低下も加わり、樹木の生育がどんどん阻まれます。これにより、草本類や低木のみが生育可能な帯が生まれ、そこが森林限界となるのです。
このように温度は、樹木にとって不可避かつ根本的な環境因子であり、成長・生存・分布に深く関わっています。樹木の適応能力や耐性の違い、温度変化に対する反応も様々、樹種による違いが森の多様性を形づくっているのです。

松が枯れている原因
松くい虫による松枯れは、マツ類に深刻な被害をもたらす森林病害のひとつです。
松くい虫とは、マツノマダラカミキリという昆虫と、それが媒介するマツノザイセンチュウという線虫の複合体によって引き起こされる病害です。成虫のカミキリムシがマツの幹や枝に産卵する際に、マツノザイセンチュウが体内から放出され、木の導管内に侵入し、その後マツノザイセンチュウは導管内で急速に増殖し、水の通り道を塞ぎ、その結果、葉が急速に変色・褐変し、やがて枯死に至ります。発症から枯死までは短く、被害の拡大も速いため、早期の対策が重要です。
この病害は、主にアカマツやクロマツなどに発生しますが、他のマツ類でも被害が報告されています。防除対策としては、伐倒駆除、薬剤注入、フェロモントラップなどが用いられています。また、発生源となる松の森林を先に伐採することも感染拡大防止に効果的です。
松くい虫被害を抑えるためには、地域が一体となり監視と早期対応が不可欠ですが、現状ではあまりに多くの松食い虫の被害があることから、予算的にも人員的にも諦めてしまっている自治体も多い状態です。

もみの木立ち枯れの問題
長野県軽井沢町(標高約1000m)では現在、ウラジロモミの枯死が多数確認されています。この現象の原因については、気温上昇によるキャビテーションやカミキリムシなどの虫害も一因として考えられましたが、これらだけでは説明しきれない可能性が高く、以下のような複合的な要因が考えられます。
まず、近年の気候変動による夏季の気温上昇が挙げられます。ウラジロモミは冷涼で湿潤な環境を好む樹種ですが、軽井沢町でも日中高めの気温が続き、夜間の気温が下がりにくくなるなどの変化が見られ、モミの木が育成するのに適さない環境になってきている可能性があります。
気候変動においては、冬季の寒暖差が大きくなっていることも原因の一つとして考えられます。冬季から早春にかけての凍上現象(シミあがり)が影響している場合、浅根性のモミ類は凍結と融解を繰り返す土壌条件で根系が傷みやすく、それによって吸水不良や酸欠を招き、結果として地上部の枯死に至ることがあります。
土壌病原菌の影響も考えられ、なかでもフィトフトラ属などの病原体による根腐れなどが、今回のモミ枯れの主要因とも考えられます。これは高湿度や排水不良な林床環境下、すなわち嫌気状態で活性化しやすく、外見上は葉が青々としていても内部では根が侵されており、急激な全体枯死を引き起こす「偽健全性」を示すことがあります。これらの菌は、気温20〜30℃で繁殖が活発となることから、過湿な土壌や酸欠状態と相まって、健全な根系にも侵入し、吸水障害を引き起こしていると考えられます。
光量との関係では、モミ類はある程度の耐陰性を持ちますが、年々暗くなる林内の光量不足が長期にわたって光合成量を減少させ、衰退・枯死に至るという例もあります。
以上のように、現在軽井沢町で見られるウラジロモミの枯死は、気候変動、根系障害、病原菌、光環境の複合的なストレスに起因する可能性が高く、単一要因では説明しきれないことから、葉の変色や落葉、形成層の色、根元の状態、土壌の菌の種類と量、林内の立地・気象・他樹種の健全度といった複数の観点から診断することが求められます。