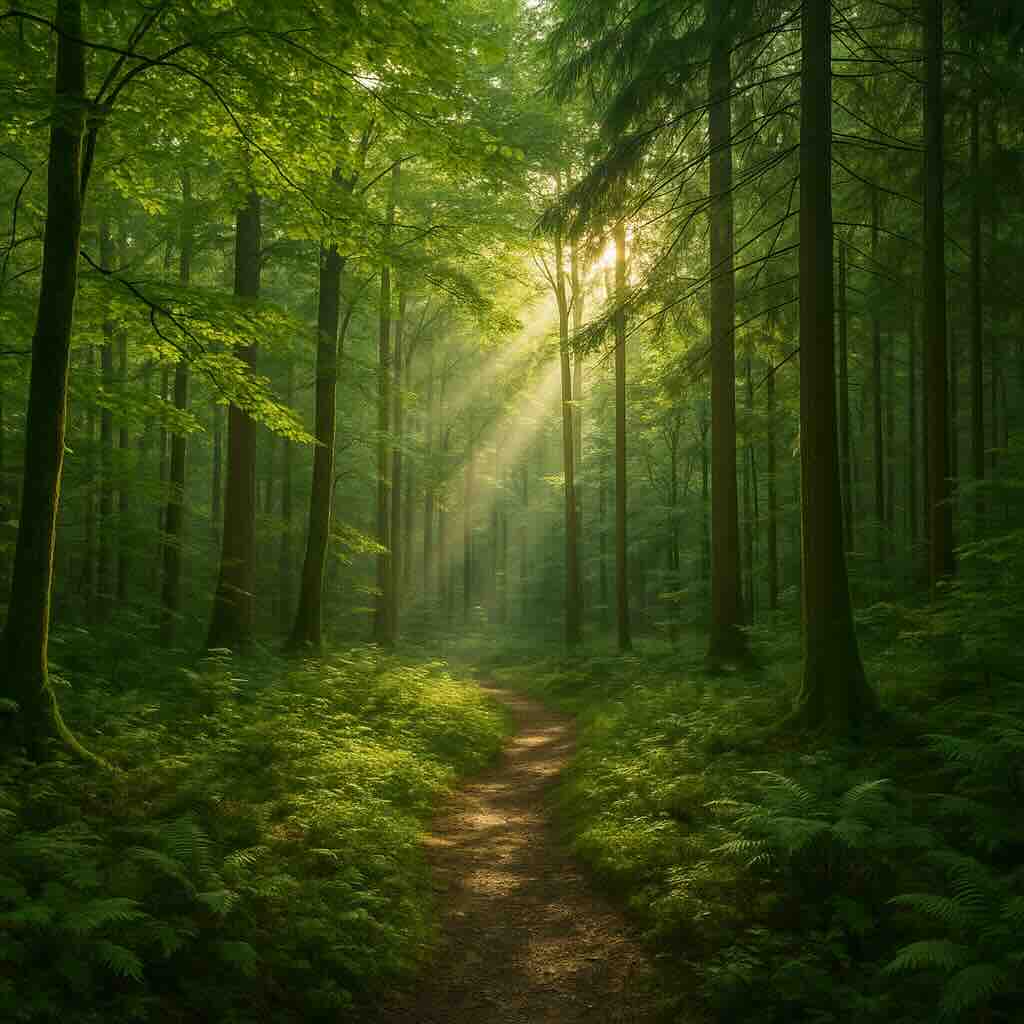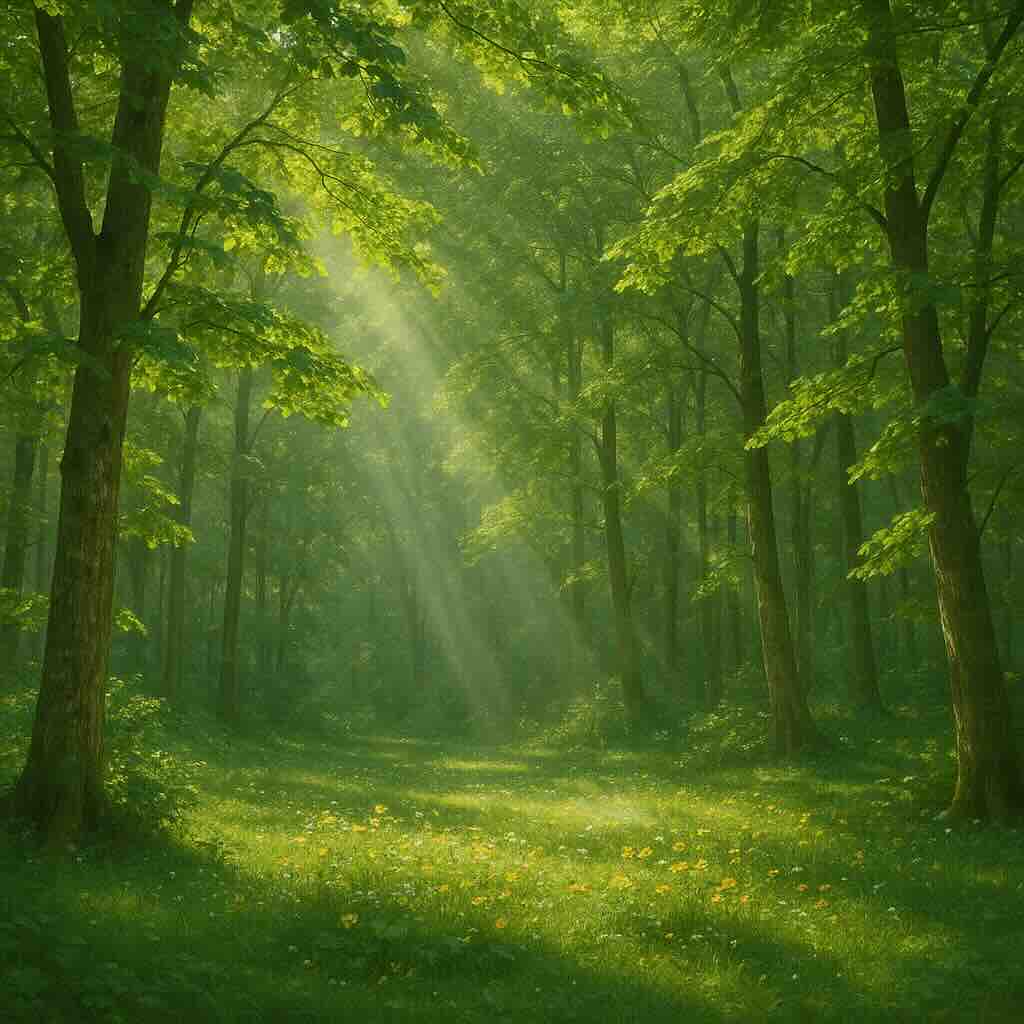森林考察
森林に対する考え方、現状からの問題提起。それに対しての私たちはどう対応するべきかを考えます。

軽井沢の森の現状
避暑地としてまた国際的な保健休養地として知られるここ軽井沢町。沢山の別荘が静かな森の中で時を刻んでおります。
別荘を建てた時は小さかった樹木も長い年月と共に胴回りを両手で測れない程の大きな樹に成長しました。
用材目的や静養地の資源として明治・昭和に植えられた樹木は、長い年月の中で人工天然林と呼べる大きな森となりました。現在の軽井沢町の森林では、大切にされてきた木々が高木や大径木となって各所に沢山見受けられるようになりました。
かつては一つの大きな森でありましたが、別荘地として細かに分譲され、個人が個人の価値観で森や林を管理するようになったことで、ある場所では過剰に保護され、またある場所では逆にまるぼうずといった状況が起こるようになりました。樹木や森への考え方や価値観はまさに十人十色ということで、森林としての適切な管理はできておりません。そして今、軽井沢の森林は成長の限界に達しており、立木の高密度化による立ち枯れや強風による風折れ・積雪による枝折れ、皆伐地への倒木の懸念が高まりつつあります。

森林保護の是非
自然を保護することは前提として勿論必要ですが、過剰な保護という名の”放置”により今や触れられないほど大きく成長したのもまた事実です。
そんな成長過多な森が起こす倒木や枝折れ、さらには極端な日陰と湿度により家屋は朽ちて、カビとキノコの温床となります。
だんだん住みにくくなるとますます放置し、最終的に住めなくなり土地を自然に奪われてしまう・・
私たちは、生活に密着する自然とは、”保護(放置)するものではなく、共存(手入れ)するものである”と考えています。保護(放置)し続ければ自然(人工林)は天然(天然林)に戻ろうとします。これは、自然即ち’森’に自分たちの住む場所をお返しすることと同義となります。自然に明け渡すことを目的としていないなら、自然と共存する必要があり、その為に適切な手入れが必要なのです。

森林伐採の必要性
天然林がなぜいけないのでしょうか。
いいえ、決してそうではありません。天然林とは、人の手が入っていない昔ながらの森を指します。または、かつては人工林であったものが誰も触らなくなり天然更新された結果の状態を指します。天然林とはどんな所でしょうか。それは鬱蒼とし暗く枯損木が溢れ、倒木や大木もあり動物たちもたくさん生息している、という状態です。そこに文化を持ち込む隙間はないと言えるでしょう。
では全部切ってしまえばいいということでしょうか?確かに伐採すること自体は一つの解決にはなるかもしれません。しかし、”森林(自然)と共存する生活”としての解決にはなりません。
そこで私たちは伐採以外の解決策を考えなければなりません。

みんなの共有財産
軽井沢町は景観そのものがブランドであり、町を超えた大きな財産です。高い建物もなければ壁の色だって決まっております。樹木に関わりを持つ方全てが、町や地域全体で一つの財産を共有しているという認識を持つことが理想といえるのではないでしょうか。
大切なのは、切りすぎない・保護しすぎない、”バランス”です。切り過ぎても、保護し過ぎてもきっとこの景観は壊れていくでしょう。
例えば枯れ枝を切るだけで危険がなくなるかもしれません。また樹高を下げるだけで、強風による倒木を避けられるかもしれません。

Arboriculture -アーボリカルチャー-
日本では木を切る人のことを”木こり”や”伐採師”はたまた”杣人””空師”なんて呼んだりします。
しかしどれも限定的な仕事を表す名前に過ぎません。
海外には”arboriculture”という言葉があります。これは直訳すると樹芸という意味があります。樹芸とは、木を植え、木を育て、木をケアし、そして木や枝を切るなど樹木に関する全てのことを指します。
木を切りもすれば育てもする、それに治療や木の周りの環境のことも考えられる、それが樹芸=arboricultureなのです。

Arborist -アーボリスト-
Arboricultureを行う人を”arborist”と呼びます。 ここで勘違いしてはいけないのが”Arborist”=”伐採する人”ではないといいうことです。先の通り樹芸を行う人のことをArboristと呼びますので、木を切る人はただ単に”木こり”=”Axman”(斧を振る人)となります。
このArboristという仕事は日本ではあまり知られておりませんが、欧米ではとてもポピュラーな仕事です。欧米で伐採をする人というのは林業か樹芸をする人のことで、その樹芸の概念”Arboriculture”が浸透しております。
Arboristが樹木に関することを全てをやるのに対して、日本では、伐採とケアと剪定は全て別々の仕事のようです。
私たちが”Arborist”と名乗るのは、事業目的の根幹は樹芸であることを前提にしているからなのです。

野生動物と人
なぜ住宅地へサル・イノシシ・クマが出没するのでしょうか。ここのところ沢山そんな話を聞くようになりました。
かつては住宅地から遠い順に奥山→里山→住宅という構図が全国どこでも当たり前にありました。里山には毎日でも人が山に入り、藪を刈り薪を拾ったりすることで、自然と林内は整理され見通しのきく状態でした。この見通しが良く綺麗な林内の状態が自然のフェンスとなり人と動物の境界帯となったのです。帯と呼ぶのは里山といわれる一つの斜面・時には山ごとが、人の住処と動物の住処のグレーゾーンだからです。このグレーゾーン、現在は殆どなくなってしまいました。人が山に入らなくなったことで、グレーゾーンがなくなり、住宅のすぐ裏まで奥山が迫るようになりました。グレーがなくなり白黒ついてしまった山と人間社会は、もちろん野生動物とも隣り合わせになります。行政や自治体は仕方がなく金属製のフェンスで山を丸ごと囲いましたが、そのフェンスによりさらに人は簡単には山に入ることが出来なくなりました。こうして、皮肉にもまるで動物園のように野生動物と人間の距離は近づいたのです。